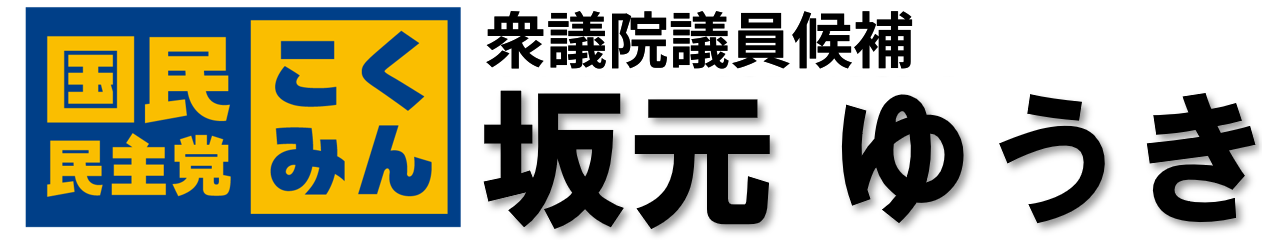目黒区がこれからの時代に求められるのは、「住みたい街」だけでなく「働きたい街」「企業が根を下ろしたくなる街」への進化です。企業が集まる地域は、安定した雇用を生み、地域経済を活性化させ、税収の増加によって行政サービスの充実にもつながります。法人の存在は街全体の活力の源となるのです。
しかし、目黒区は他の23区と比べて法人の数が少なく、経済基盤の強化という点では課題を抱えています。中目黒におけるグローバルスタートアップキャンパスの設置を中心とした再開発をはじめとする都市整備の好機を捉え、インフラ整備や子育てや介護支援制度を進め、企業が目黒区に拠点を構えたくなるような土台づくりが急務です。働きやすく、暮らしやすい環境を両立させながら、起業やスタートアップ支援にも積極的に取り組んでいきます。
多様な才能が集まる街に
小1の壁の打破!(7時から19時まで)シームレスな保育で女性活躍の街へ
朝7時から夜19時まで、お子様や要介護者を預けることができれば働けるのに、という方がたくさんいらっしゃいます。労働力不足が叫ばれている中、働きたいと思う方や協力的な企業を支援する街であるべきです。
シームレスな子どもの預かり
お子様の預ける場が3-5歳は保育園、6-12歳は小学校、13-15歳が中学校とステージが変わるたびに大きなライフサイクルの変化があり、親の働き方に大きな影響を与えることが大きいです。例えば、目黒区の保育園では朝7時15分から預かってもらえていたのに、小学校に上がることによって朝の時間、安全な場所に預けることができなくなってしまいます。朝早くから校門を開けている小学校もありますが、その対応は各学校ごとに委ねられているため一律的ではありません。
また、放課後の学童は19時まで対応されているところが多いですが、定員数がまだまだ足りず募集に落ちてしまう可能性があります。月額制でもあり、この日だけ必要と言った要望には答えてもらえないなど不便な点も指摘されています。ランラン広場という放課後の学校開放システムもありますが、預かってもらえる時間が17時までに限定されてしまいます。
そのため、働くのはお子様が小学4年生くらいになってから、と言った考え方が生まれてしまっており、労働供給の面からしても問題と言わざるを得ません。
1歳半から小学4年生までは朝7時から夜7時までシームレスに子供を預かれる環境を整備する。そのために小学校の朝広場(仮)とランラン広場の拡充し待機学童をなくし、一時預かりも可能に。
要介護者や障がい者、医療的ケア児を抱えていても働ける街
就労の足かせとなってしまっているのは子どもの預け先の問題だけではありません。介護離職として社会問題化している介護の問題、障がい者や医療的ケア児を抱えている親の就労率が低いのは問題となっています。介護は7時から19時まで預けられるデイサービスの拡充が必要です。しかし、今の保険点数や人材不足ではこの時間に対応しようというデイサービスはありません。早朝加算、ナイトサービス加算、デイサービスからデイサービスへのはしごサービスなどを解禁などが必要です。
また、施設入所が必要な方を抱えているために就労を諦めている方が非常に多いです。いわゆる介護離職者問題です。目黒区に大規模な特養を作る土地はありませんので、小規模施設活用や民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅への入居を補助する制度で就労者への支援を行うべきです。
医療的ケア児の親御さんの多くが通学や学校内での世話などを行っているケースがまだまだ多いです。支援員や看護師等の配置を熱くし、保護者の負担を減らす必要があります。
・介護離職をなくすーー働きながら介護できる社会へ
日本では、年間10万人以上が「介護離職」を余儀なくされています。これは、親や配偶者などの介護を理由に、働き盛りの世代が仕事を辞めざるを得ないという深刻な社会課題です。少子高齢化が進む中で、働き手の減少に拍車をかける「介護離職」を放置することは、日本全体の生産性を下げ、介護する側もされる側も不幸にしかねません。
介護人材の確保には「家賃補助」が効く
まず根本的な課題として、介護職員の慢性的な人手不足があります。都心部では特に、給与と生活費のバランスが取れず、働き手が定着しない問題が顕著です。
そこで私は、介護職員への家賃補助制度を強化するべきだと考えます。目黒区内の賃料相場は都内でも高水準にあり、若い介護人材が定住しづらい現状があります。区として、介護職に従事する方へ月額上限付きの家賃補助を導入・拡充することで、現場の人材確保に繋げることができます。
これにより、地元で安心して働ける環境が整い、結果的に介護サービスの質と供給の安定化にも寄与します。
企業が「介護と仕事の両立」を支える制度へ
もう一つの要点は、働きながら家族を介護する人が辞めずに済む「制度の整備」です。介護休暇や時短勤務などの制度は存在しているものの、取得しにくい雰囲気や実際に収入が減ることへの不安から、制度が活用されていないのが現実です。
そこで提案したいのが、介護休暇を積極的に取得できる企業へのインセンティブ制度です。例えば、介護休暇取得実績のある中小企業への助成金、区独自の表彰制度などを設けることで、介護に理解のある企業文化の醸成を後押しします。
さらに、リモートワークやフレックスタイムの推進も、介護と仕事の両立には欠かせません。自治体から企業への啓発・相談支援を強化し、働き方の選択肢を増やす環境整備を進めてまいります。
介護離職ゼロの街を目指して
介護は、誰にでも起こり得るライフイベントです。目黒区では、高齢化の進行とともに介護を担う世代も多様化しています。働きながら介護ができる環境整備は、単なる「福祉政策」ではなく、「労働政策」や「地域経済政策」にも直結する重要な柱です。
私は、介護職への家賃補助と、企業への支援策の両面から、「介護離職ゼロのまち・目黒」を目指して全力を尽くしてまいります。
先端ビジネスへ攻めの規制緩和を
スマートシティと聞くとまず思いつくのが、自動運転の車が渋滞も事故もなく走り回るシーンではないでしょうか。アメリカや中国、ヨーロッパでの実証実験が進んでいるニュースを見ることが増えてきましたが、日本の状況は少し遅れているように思います。日本は実験的な運用に省庁が許可を出さなかったり、高品質な通信環境や道路の整備などの遅れにより技術は備わっていてもその実証実験は、自動車大国である割に進んでいないように思います。目黒区でも新しいアイデアに対して門戸を開き共にビジネス化するくらいの仕組みが必要です。
データの収集や利活用にも現在制限が多いです。上であげたヘルスケアデータの集約もそうですが、税や社会保障のデータも一元化されてもなく、民間で利用することも出来ません。当然プライバシーに考慮したうえでですが、ビッグデータをいち早く利用できる環境にしていかないと海外のプラットフォームに根こそぎ先を越されてしまいます。
また、大企業の本社機能を誘致するためには駅や高速道路に近く大規模なオフィスを取れる不動産の確保が必要です。大規模な不動産の開発に関しても街の緑を減らさないことなど一定のルールはつけたうえで推進するべきです。
ICT・DX化推進で効率的な事業運営の支援
行政サービスも少しずつICT化が進んでおり、目黒区でも転出届や国民健康保険の加入の手続きやコンビニで住民票や印鑑証明書を取得できるようになりました。今後はより細かな行政手続きや税や保険の支払いなど様々なことがオンラインで出来るようになれば個人だけでなく法人にとっても大きな恩恵を受けることができるはずです。
今後は例えば、個人の医療介護情報などを一元管理することで、効率的な治療計画や薬の副作用が起きないような管理が可能になります。また、ノウハウが溜まれば病気の先回り的治療や介護予防に役立てることが可能で、先般問題となっている医療費や介護費の伸びを吸収することが可能です。例えば、患者にウェアラブルウォッチなどを常時つけてもらい、対応や血圧などの日々の健康状態の情報をクラウド上にアップロードし続けることで日々のデータを集め同時にAIによる分析を行い、体調の変化を感知します。そのためには高速通信ネットワークの維持やクラウドデータベースのセキュリティの管理など様々な情報インフラの整備が必要になります。
現在東京都ではGovTech東京が自治体DXや業務の共有化にチャレンジしています。私もICT・DX化の推進に協力していきたいと思います。