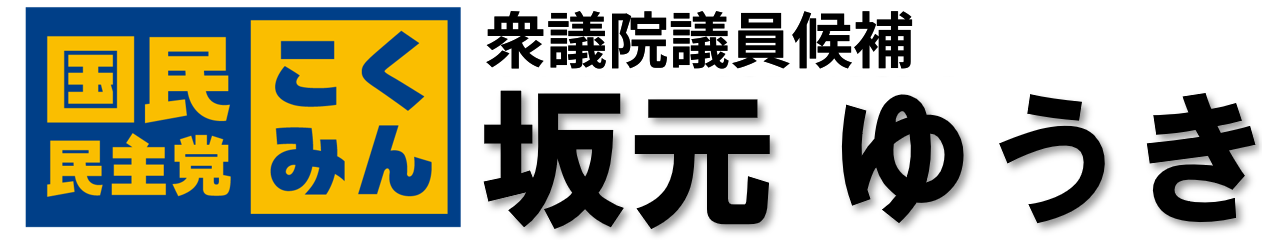私たちは今、かつてないほど目に見えない脅威に囲まれて生きています。かつて国家の防衛とは、陸海空の軍備を整えることでした。しかし21世紀の現代においては、もはやサイバー空間も「戦場」の一つと化しています。ミサイルが飛ばずとも、電力網が止まり、行政システムが麻痺し、企業の機密が盗まれることで、国家の機能が崩壊するのです。
すでに世界では、他国のインフラを標的としたサイバー攻撃が常態化しています。アメリカでは病院の情報システムがランサムウェアにより停止し、ドイツでは行政システムが一時麻痺しました。日本も例外ではなく、防衛省や企業が狙われた事例も記憶に新しいところです。
問題は、これらの攻撃がしばしば国家単位で行われている可能性があるという点にあります。つまり、サイバー攻撃とは単なる犯罪ではなく、事実上の「準戦争行為」なのです。しかしながら、我が国のサイバー防衛体制はいまだ十分とは言えません。官民の情報共有は限定的であり、法制度も「攻撃」ではなく「防御」一辺倒の枠組みにとどまっています。
サイバーセキュリティにおける国家戦略の再構築を
サイバー空間において国家を守るには、これまでの「情報システム部門まかせ」の対応では限界があります。今こそ、国全体の安全保障戦略の一環として、サイバーセキュリティを再定義しなければなりません。私は以下の4つの柱を軸に、国家として本格的な「サイバー防衛体制」の確立を訴えます。
① 技術人材の国家育成と戦略的配置
日本は技術者の待遇や社会的地位において、欧米・中国・インドに比べて大きく遅れを取っています。国家防衛の中核として、サイバー分野の人材を「準軍事的人材」として育成・登用すべきです。防衛大学校や情報系の国立大学にサイバー防衛専門課程を設置し、国家資格化・階級制度の導入を検討します。また、地方自治体や中小企業における人材不足にも対応するため、「地域サイバー防衛隊(仮称)」の創設も視野に入れます。
② 官民連携の危機対応ネットワーク構築
重要インフラの多くは民間企業が保有・運営しており、官民の分断は深刻なリスクです。よって、情報通信、金融、エネルギー、交通、医療などの分野ごとに、民間大手と政府・自衛隊・警察・自治体が参加する「インシデント即応連絡網」を制度化し、定期的な訓練と演習を義務づけます。災害対策基本法に準じた「サイバー緊急事態基本法」の制定も必要です。
③ 防衛産業の国産化と技術主権の確保
我が国は重要なセキュリティ機器や通信技術を外国製品に依存しています。この状態は「平時の利便性」を優先した結果であり、非常時には重大な脆弱性となります。安全保障に直結する分野においては、国産技術への移行と国内サプライチェーンの再構築を進めます。また、半導体、暗号技術、OS開発といった基盤領域には国家主導で資金と人材を集中投資すべきです。
④ 法整備と倫理的規範の両立
サイバー攻撃の多くは、技術的な手口よりも「法の想定外」を突いてきます。従来の刑法や不正アクセス禁止法だけでは対処しきれないため、「国家機密保護法」「経済安全保障法」の強化・拡充といった法整備を進めます。一方で、濫用防止と国民の自由を守るため、監視のあり方には明確な倫理規範と国会による厳格な監視体制を整える必要があります。
国家を守るとは何か
私たちは、目に見える戦車や戦闘機には敏感でも、目に見えない「情報の戦場」にはどこか無防備です。しかし今や、戦争は銃弾の飛び交う戦場ではなく、静かなる画面の向こうから始まる時代となりました。金融システムの一時停止、電力網の寸断、医療機関の情報漏洩、交通制御の麻痺──こうした事態が起きるだけで、国家の機能は麻痺し、国民生活は瞬時に崩壊します。
サイバーセキュリティとは、単にパソコンやスマートフォンを守ることではありません。それはすなわち、国民の生活基盤を、ひいては国家そのものの尊厳と独立を守る行為にほかなりません。
我が国は、長く「平和国家」としての自画像を大切にしてきました。しかし平和とは、備えなき理想ではなく、覚悟ある現実によって初めて維持されるものです。サイバー攻撃という新たな脅威の時代に、私たち政治家が果たすべき責任は明確です。目先の便益ではなく、国家百年の計としての安全保障政策を練り直すこと。その第一歩が、サイバー空間の統治と防衛なのです。
私は、自由と秩序を守り抜く強靱な日本のために、サイバーセキュリティ政策の抜本的強化を政治の場から訴え続けます。国民が安心して暮らし、企業が正々堂々と挑戦できる社会、それを支える静かなる盾──それが、いま我々が築くべき「令和の国防」であると確信しています。