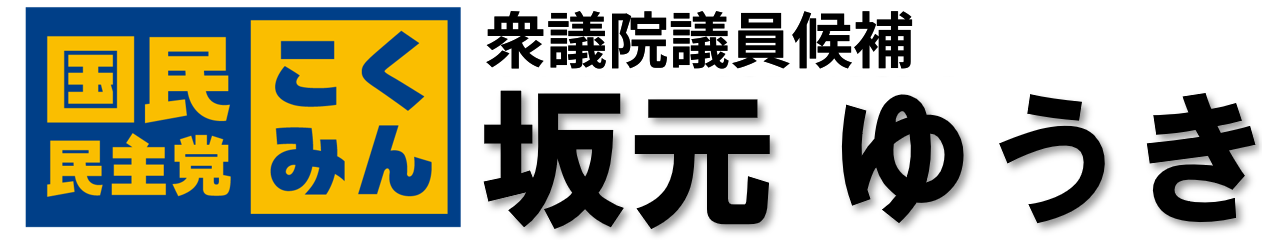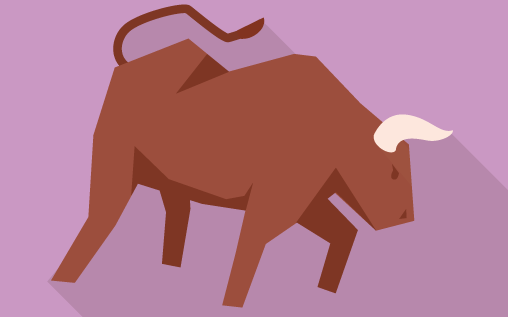「力による現状変更を許さない」──この言葉が国際社会で繰り返されるようになったのは、決して偶然ではありません。第二次世界大戦以降、世界は国際法と国連憲章を基盤に、主権と領土の不可侵を原則とする秩序の構築を進めてきました。しかし近年、この秩序が根底から揺らいでいます。
その象徴が、2022年に始まったロシアによるウクライナ侵略であり、また中国による台湾海峡・尖閣諸島への軍事的・経済的圧力です。21世紀に入ってなお、「武力」を後ろ盾に国際秩序を塗り替えようとする動きが、常態化しつつあります。
表向きは「国際的非難」に晒されていても、実際にはその代償が十分でないために、指導者はなおも強硬姿勢を取り続けています。すなわち、「力による現状変更がコストとして割に合う」状況が続いているということです。
■「損をする世界」こそが抑止力の本質
では、真に「力による現状変更を許さない」世界とは、いかなる世界でしょうか。それはつまり、「力による現状変更を試みた者が、必ず大きな損失を被る世界」です。しかも、その損失は国家全体ではなく、決定権を持つ“国家の責任者”が直接的に被る構造でなければなりません。
ここで重要なのは、民主主義国家と専制国家の違いです。民主国家では、指導者は選挙によって責任を問われますが、専制国家では一人の独裁者が国民の犠牲を顧みず、戦争を決断することが可能です。よって、抑止力を構築するには、独裁者本人にとって「戦争に踏み切ることが致命的な誤算となる」ような国際体制が必要なのです。
そして、ここで言う「損」とは、単なる経済制裁にとどまらず、軍事的手段による強硬な報復を含むものであるべきです。つまり、武力侵攻が始まった段階で、侵略者に対して「侵略を継続すれば、自国が壊滅的被害を受ける」という現実的なプレッシャーを与えなければなりません。これこそが真の意味での抑止力です。
■国際秩序の再設計には現実主義が必要だ
残念ながら、現時点においてそのような抑止体制は整っているとは言えません。国連は加盟国の多様な利害の中で動きが鈍く、安保理常任理事国であるロシアや中国が拒否権を持つ限り、その機能には限界があります。経済制裁も、多国間の協調がなければ抜け穴だらけとなり、侵略者に十分な打撃を与えられません。
私は、戦争を本気で防ぐためには、国際社会が今以上に現実主義的でなければならないと考えます。理想だけで戦争は止まりません。必要なのは、「侵略をすれば破滅する」という鉄の原則です。そのためには、平和時からの軍事的な連携、技術共有、外交圧力、サイバー防衛、そして経済制裁の即時発動体制といった多層的な抑止網の構築が不可欠です。
■外交・安全保障は国家の根幹である
現在の日本は、経済再建や少子化対応など、内政課題に目を奪われがちですが、だからこそ外交・安全保障こそ政治の最優先課題であると、私は強く訴えます。国家が外圧に屈すれば、内政の成果も一瞬で吹き飛ぶ。平和の維持には、「人・モノ・金」、そして国家意思の集中が求められるのです。
人類はまだ、戦争を完全に防ぐ知恵も制度も持ちえていません。だからこそ、政治はその限界を直視し、戦争に踏み切る余地を一歩一歩減らしていく責任を担っています。「力による現状変更を許さない」世界の実現は理想ではありません。それは、我々がこの時代においてなすべき現実の課題であり、日本が果たすべき歴史的使命でもあるのです。