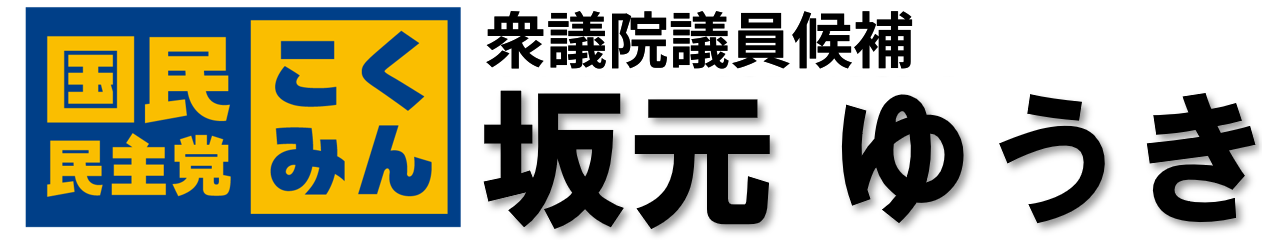令和の時代に入り、日本を取り巻く安全保障環境は著しく不安定化しています。中国の海洋進出、北朝鮮のミサイル発射、台湾有事への懸念、そしてロシアによるウクライナ侵攻。これらの動きが、世界秩序の根幹であった「国際法による平和」の危うさを浮き彫りにしています。
こうした状況下、日本政府は防衛費の大幅な増額を決定しました。防衛力の強化という大義の下で、5年間で43兆円超という規模の予算が組まれました。しかし、私はこの「防衛費増額」について、内容を慎重に吟味する必要があると考えています。
まず、増額そのものに対しては一定の理解を示します。国を守るためには、必要最低限の備えは不可欠です。特に、自衛隊員の処遇改善や老朽化した装備の更新、弾薬や燃料などの基本的な備蓄の充実は、現場の安全と任務遂行の基盤であり、優先すべき分野です。
ところが現在の防衛費の増額には、疑問の残る使途が目立ちます。高額な米国製兵器の大量購入、ミサイル防衛システムの導入、米軍への「思いやり予算」の上積みなどがその例です。これでは「防衛強化」というより、米国の軍需産業の後押しとも映りかねません。
本来、日本の防衛力とは、自衛隊が日本の地に根ざし、日本人の手によって、自国を守るために整備されるべきものです。他国の戦略や経済的都合に流され、主権ある国家の防衛を委ねてしまっては本末転倒です。
特に看過できないのは、自衛官の給与水準の低さです。
自衛官は、災害対応から国防まで命を懸けて任務にあたっています。しかし、その待遇は決して十分とは言えません。任期制の若手自衛官では年収300万円台というケースも珍しくなく、結婚や家庭の形成に不安を抱えながら任務に従事する姿があります。また転勤が多く、単身赴任や子育ての困難さに直面している隊員も多いのです。
このような処遇では、有為な人材の確保も難しく、士気の維持にも影響が出かねません。防衛力の根幹は人です。どれほど高性能な兵器を導入しても、それを使いこなす隊員が疲弊していては、真の防衛力とは言えません。
今、必要なのは「人への投資」です。国産技術の育成や先端分野の開発と並び、現場を支える自衛官の待遇改善を最優先にすべきです。防衛費を増やすならば、まずはそこに税金を充てるべきであり、「額」ではなく「中身」を問う議論が、今こそ政治に求められています。