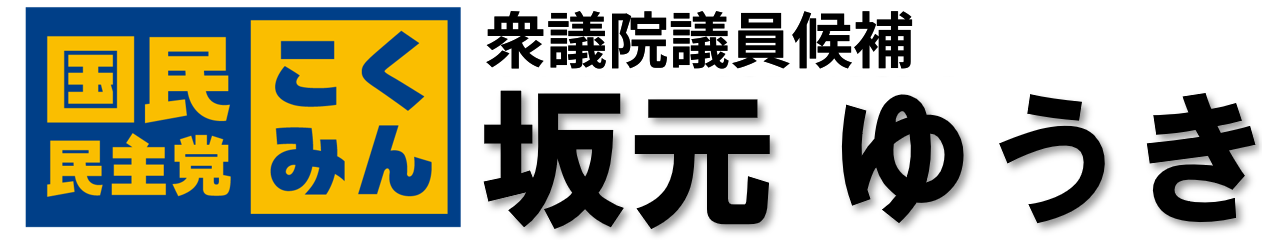経済政策は国民の気質によって効果が変わることがわかっています。特に日本人はアメリカなど欧米人と違った反応を見せることがあり、その特性を見極めて政策を決定する必要があります。
経済学が過去のエビデンスとして上げてくるデータの多くはアメリカやヨーロッパのものであり、経済学のセオリーが通じないことがあるということです。
消費税は日本人にとって一大事
例えば、消費税の増税は他国と比べて日本人にとって悪影響が強い傾向があります。
日本では消費増税が行われるたびに明確に消費減退が確認(1997年3%→5%、)できますが、同じく消費増税を行ったイギリス(2010年1月15%→17.5%)やドイツ(2007年1月16%→19%)、イタリア(2011年9月20%→21%)の例を見ても大きな減退が見られないのです。
このように日本人にとって消費税の影響力は他の税金や社会保障費と比べてとても高い傾向があるのです。
こういった現象を消費税の弾力性が高いと表現します。
簡単に言えば、消費増税は他の税金に比べて極端に景気を刺激するということです。
その理由の考察は様々な経済学者が行っていますが、実際の家計への負担以上に「消費税」というキャッチーな名前や連日ワイドショーなどで議論されることによる心理的効果が大きい事も要因ではないかと思います。
消費減税の弾力性はいかに
ここで、出てくるのが反対に消費減税がどのような影響を及ぼすのかという疑問です。消費増税に過度に反応してしまう国民性が消費減税に対しても過度な反応(消費続伸)を見せるのか興味があるところです。
消費減税の議論は特に野党側から幾度となく提案されていますが、未だに実現された試しはありません。
私は経済政策の弾力性が高いと思われる消費減税をぜひやるべきだと考えています。消費減税という政策が消費増税並に消費への影響を持つものなのか、実験的な意味合いを持つかもしれません。
消費税の減少分以上に他の税金で賄うことができるかもしれません。
消費税の流動性
当然店舗などのシステムを整える必要がありますが、消費税を流動的に増減させることができれば、経済政策の手段として利用することが可能になります。
また、流動性を与えること消費が加熱し物価が上がってしまった際に消費税を上げることでインフレに対する対策としても機能させることができるかもしれません。